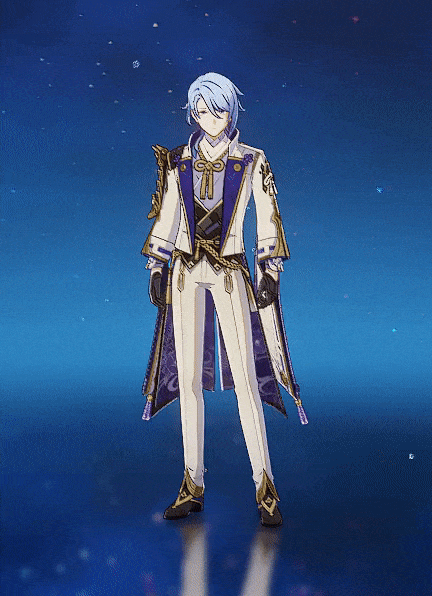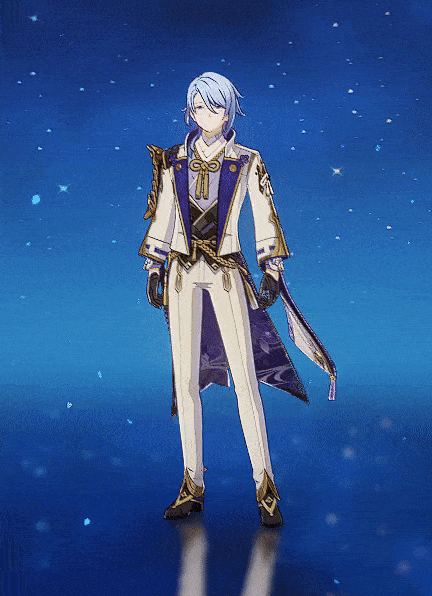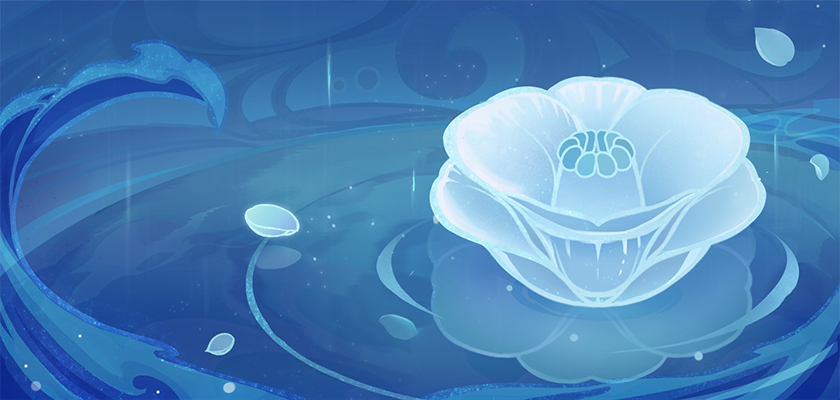キャラクター詳細
三奉行の一人——社奉行神里家当主、神里綾人の名を稲妻で知らぬ者はいない。
しかし、優雅で心優しい「白鷺の姫君」綾華とは違って、兄·綾人に対する民衆の認知ははっきりとしたものではない。
人々はただ、彼が幕府の重鎮であり、名門貴族の当主であることしか知らないのだ。彼の詳細について聞かれた時、誰もが皆口をつぐんでしまう。
ある者はこう言う——「社奉行が主催する祭事や催しは、少しも手抜かりがない。それに、近隣住民の面倒もよく見てくださる。きっと奉行様の苦労あってのことだろう。」
しかし、またある者は言う——「ちっ、官界には公にできないもんが数多くある。裏のやり口を知らなけりゃあ、高官になんてなれないのさ。」
ただ、それらの言葉を神里綾人本人は気にしていない。
「私はただ…将軍様の下で真面目に仕事をし、職務を全うする役人に過ぎません。」
キャラクターストーリー1
稲妻名門の長男である神里綾人は、生まれた時から愛されて育ってきた。
両親は執務で忙しく、常にそばにいるわけではなかったが、それでも彼の面倒をよく見ていた。もちろん、日頃から「坊ちゃま」に色々と気を配ってくれた者も数多くいた。
年を重ねて少し大きくなると、綾人は父の求めに応じて、一族の「後継者」に足る能力を基準とし、複雑で難解な勉学に励んだ。
しかし、負担の大きな政務と一族復興の重圧から父は過労で重病を患い、不幸にも早くに逝去してしまう。
まだ年若かった綾人は、一族の地位が危機に瀕している中、権力争いの渦中へと身を投じることになったのである。
当時、まだ駆け出しであった若き青年に期待の目を向ける者など誰一人としていなかった。神里綾人は裕福な家で育った貴公子から、巷で噂される「神里家の可哀想な坊ちゃん」、そして政敵からは鼻で笑われる「見込みのない小僧」と呼ばれるようになった。
だが、その者たちの考えが間違いであったと、時間が証明することとなる。
当主の跡を継いだ神里綾人は、並々ならぬ大胆さと一流とも言える手腕によって、神里家の衰退をくい止め、一族の地位をより確固たるものにしたのだ。
手が回らなくなるほどの激務や悪意の潜んだ欺瞞、至る所に蔓延る詭謀…彼はそれらすべてを払いのけ、さらには自らに有利に働くよう利用した。
時が流れ、幕府と民から寄せられる社奉行神里家への声誉は、ますます高くなった。
今の神里綾人は紛うことなく、稲妻名門の筆頭格たる神里家の「当主」であり、要職に身を置く「社奉行様」だろう。
キャラクターストーリー2
社奉行は鳴神の祭祀を司り、また文化や娯楽活動の管理をしている。神に通じ、民衆と心を通わす、筆頭格に恥じぬ存在だ。
無論、携わる領域が広まれば、仕事の量が増えるのは必然のこと。
ただ幸いにも、妹の綾華が兄に代わって家業の大半を引き受け、社奉行と民の間でされる交流をほとんど担ってくれている。そのおかげで、綾人はより政務に専念できるようになった。
幕府の役人との交渉は簡単なものではない。所属する奉行、一族、立場、そのすべてが各々で異なっている。一つの事柄に対して関わる者が多ければ多いほど、それを遂行するのは困難になる。
綾人の強みは、それら事柄の対処に長けているところだ。彼からしてみれば、人の行動はすべて利益に準じたものであり、要所さえ押さえていれば、相手を妥協させることができるという。
標的に狙いを定め、相手を自分の理論に引き込む。そして建前を織り交ぜながら諭し、少しばかりの恩を売れば大方の問題は解決する。
もし仮に相手が考えを変えない頑固者であっても、より強い勢力を引き合いに出して制圧すればいい——どれだけ地位が高く、尊大に構えていようとも、天の威光を揺るがせる者などいない、そうは思わないだろうか?
教養があり、礼儀を知る神里家当主は、やがて幕府の中で高い名声を手に入れた。
「これは…なかなかに難題だな。社奉行様に聞いてみたらどうだ?」
人々は常々そう口にする。
ただ、数多の手段を持つ綾人ではあるが、いつでも手を差し伸べるというわけではない。
すべての事柄が社奉行と関わっているとは限らないからだ。その上、他の勢力の僅かな利益のために、神里家を巻き込むのは割に合わないだろう。
大半の場合、綾人が熱い茶を手に持ちながら微笑みを携え、相手を立てつつ話に付き合うだけに留まる。
「まあまあ、長岡様、そう腹を立てる必要はございません。皆さん将軍様のために動こうとしているのです。他意など誰も持ってはいません。腹の内を明かして話し合えば、必ずや共に解決できるでしょう。」
キャラクターストーリー3
その身分と仕事の制限から、神里綾人が人前に姿を見せることはあまりない。町中を出歩く時間も滅多に取れないほどだ。ただ、それら制限は彼の新しいものを追求することへの妨げにはならない。
——朝起きて剣の稽古をしていると、たまに八重堂の者が門の外からこちらの様子を伺っているのが見える。どうやら、また「報告の作業」に来たようだ。そんな時は気付かぬふりをして、彼女がどのような新しいサボり文句を口にするのか聞く。機会があれば、それを「さりげなく」八重宮司に伝えるのもいいかもしれない。
——天守閣へ足を運び、時代後れの頑固者たちと会合をする際、発言を急ぐ必要はない。いい歳をしながら顔を赤くし、些細な利権や利益で争っているのを見るのは、実に愉快だからだ。
——町の辺りまで来て、ふと独特の感性を持つ屋台があることを思い出す。新しい料理はないか、商売はうまくいっているかを店主に尋ね、新商品を試しに買って味見をする。それが興味深いものであれば、家の者にも少し持ち帰る。
——近ごろ花見坂一帯でよく見かける鬼族の青年は、虫相撲の腕があまり達者ではないようだ。親切心から少し励ましの言葉をかけてやり、彼を立ち直らせる。何気ない雑談の中で、この赤鬼が「綾人」という名が何を意味するのか知らないことに気付いた…だがそれでいい、改まって説明する必要などない。
——帰り道、鎮守の森を歩いていると、妖狸にいたずらされている通行人を偶然見かけたため、その幻を見破った。もしも今後、妖狸たちの変化の術がより熟練されることになったら、自分に感謝してほしいものだ。
——たとえトーマほど有能な者でも、夕食の献立が思い浮かばない日がある。そんな時には、鍋遊びを提案する絶好の機会だろう。綾華は毎回、予想だにしない食材を入れてくる。さすがは自分の妹。
これらすべてが、社奉行様の楽しみなのだ。
キャラクターストーリー4
執事と家司の尽力により、神里屋敷は内も外も整然としている。しかし、ただ一か所を除いて——
神里綾人が使用した後の文机は、いつも散らかっているのだ。
無造作に広げられ、そのまま伏せられた本。雑多に積み重ねられた大小様々な書類。使用後の硯と墨汁も片付けられておらず、文机の下には将棋の駒や紙札が散らばっていることもある。
当主様が執務を終えると、使用人たちは毎回、文机や書斎の片付けに時間を費やすことになるという。
その時、乱雑に置かれた紙の間に小さな便箋が挟まっているのをよく見かける。手に取ってそれを見てみると、便箋の筆跡はすべて異なり内容も様々。
「若、家来からまた新鮮な花が届きました。花瓶を置くために机の一角を少し片付けておいたので、また倒してしまわないようお気を付けください。」
「当主様、本日は鳴神大社の巫女がいらっしゃいました。宮司様からお願いがあるそうです。とても重要なことらしく、離島の一部地区の収用に関する内容のため、神社へとご足労いただきたいとのことでした。」
「奉行様、『百代』未だ枯れず。枝はまだ伸びております、ご安心を。」
「お兄様、この間、旅人さんと一緒にお祭りへ行き、新しい料理を覚えました。旅人さんが異国からいらしたことを考慮して、料理に手を加えるべきか迷っています…お兄様はどう思いますでしょうか?」
「当主様、使用人たちではこの件を口にする勇気がないようなので、この婆やからお伝えさせていただきます。食べたいものがあれば、どうぞ何なりと家司にお申し付けください。勝手に厨房の食材を使うのはどうかご遠慮いただきたく存じます…当主様に料理をさせるわけにはいきません。皆が困惑してしまいます。」
神里綾人は多忙なため、朝早くに出て、夜遅くに帰ることが多い。彼に会えない時、神里屋敷ではこのようにして彼と連絡を取っている。
これは綾人が考えた方法である。神里家ではこの小さな便箋が、屋敷全体を支えているのだ。
ただ残念なことに、この方法を使うと元より散らかっていた当主様の机が、さらに散らかることになる…しかし、気にすることはない。これは些細な犠牲に過ぎないのだから。
キャラクターストーリー5
稲妻では、とある柏木の葉を神に捧げて祈ることがある。
ただ、神を祀る儀式は稲妻に数多とあるため、規模の小さいものはよく見過ごされてしまう。
もう随分と昔のことだが、綾人には今も忘れられないことがある。それは母から聞いた話だ。その柏木は常緑の高木であり、葉は針状ではないらしい。
葉は大きく、葉脈もとてもくっきりとしている。新たな葉が芽吹いても、古い葉が色褪せることはない。
そのため、それは「繁栄」を意味し、古くは食べ物を捧げる際の器としてよく使われていたそうだ。
現在では料理の盛り付けに葉を使うことはなくなったが、柏木の葉を捧げる習慣はそのまま残っている。
趣味の影響か、あるいは元より見聞が広く、知識が豊富だったからか、母はそれら祭礼のことになると淀みなく流れるように語る。
「神里家が代々社奉行を管理しているのは、生まれながらにして神を守る存在だからかもしれないわね。」
それに対して、幼い頃の綾人は完全に同意することができなかった。
神里家は神里家であり、家族のいる場所であると彼は考えていた。一族は家族がいてこそ存在するのであって、神に仕えることはただ流れに従って行う仕事に過ぎない。
しかし、このようなおこがましい考えを口になどできなかった。それに、興に乗って話をする母を遮るのはとても忍びない。
母がどんなに長く話しても、綾人は母の前に正座し、足が痺れても最後まで静かに聴いた。
歳月は流れ、綾人が成長すると、日々の時間を剣術と書物に費やした。「講師」は母親から父親に変わり、内容も祭礼の知識から一族の後継者に求められる必須科目へと変わった。
一族の責任という概念が、次第に綾人の生活における割合を占めていく。「雷電将軍」への認識も、もはや童心の中に浮かぶ幻想ではなく、正真正銘実在する神——稲妻の永遠と平和を守る大御所様となった。
「かつて、鳴神の恩恵を受けたことで、神里家は今日まで存続することができた。そのため何があろうとも、神里家は『永遠』の道を守護し、永久に将軍様に付き従う。」
「これは既に定まった約束であり、破ることの許されない一族の掟。しかと心に刻んでおきなさい。」
先祖の教えを読んでいた綾人は、その理由を既に少し理解していた。神里家の先祖が職務を疎かにした結果、国の重要な宝である「雷電五箇伝」に多大な損失を及ぼしてしまったのだ。八重宮司の進言によって将軍様の許しを得られていなければ、神里家は他の没落した有力者たちと共に消滅していただろう。
これは大御所様からの恩賜であり、神の眷属からの警告だった。
そのため、父の教誨に対して、神里綾人も当然それを踏み外すようなことはしていない。一族を守るという信念が何より大切であろうとも、彼は道理を弁えている——稲妻は雷神の守護により存続しており、稲妻の安定のみが、一族の長きに渡る繁栄を保証できる、と。
今後、稲妻の情勢がどのようになろうと、神里家だけは御建鳴神主尊に反旗を翻してはならない。
たとえ異議を心に秘めていようと、水面下深くにある暗い川の中に隠すのだ。
そう、かつて母が言っていたように——
神守の柏は古き枝をそのままに、新たな材へと生まれ変わる。
庭の椿は冬に呑まれることなく、澄んだ香りをかもし出さん。
夢見材筆箱
幼い頃にもっとも退屈であった習字の授業が、今や良い暇つぶしになるとは、神里綾人本人でさえ思っていなかっただろう。
昔、秀麗な字を書くために練習に励んだのは、神里家長男たる身分に相応しくあろうとするためであった。
しかし今、様々な詩歌を時折模写するのは、思考を整理して静かに考える時間を自分に与えるためになっている。
もちろん、それ以外にも理由はある。手の空いている時でもまるで政務に追われているかのように見せることで、面倒なことや会いたくない者を後回しにしているのだ。
やがて、彼の身の回りの世話をする使用人たちは、当主様は将棋以外にも書道を趣味にしていると思うようになった。
そして、この話は人づてに広まり、多くの人が知ることになる。慶事や誕生日が訪れると、綾人のもとには良質な筆が贈り物として届くようになった。
しまいには、精巧で高価な羽毛筆を国外から仕入れ、奉行様に喜んでもらおうとする投機的な輩も多く現れる。
それに対し、綾人も特に説明をすることなく、精美な木箱を購入してそれら文具を収納した。
彼は元より目新しく珍しいものを好む。そのため、多種多様な新しい筆を試せるのは、実に愉悦を覚えることなのだ。
それに、様々な出自の贈り物には、贈り主に関する情報が含まれていることが多い。これら情報は綾人が彼らを掌握する手段の一つとなっている。
この筆箱は文具の収納のために買ったものだが、三つの特別な筆だけは未だその中に入れたことがない。
一つは作りが丁寧で、筆の持ち手は細く、社奉行の文机の上に直接置かれている。多少傷みはあるものの、書き心地はとても軽く滑らかであり、公文を書くのに使用している。
二つ目は、文机の一番下の引き出しにしまわれており、筆先が少し毛羽立っている。かつて愛用していたもので、子供の頃の習字の際に綾人が選んだものだ。初心者向けであるため、以前はよくトーマと綾華が借りていた。
三つ目は、骨董品が保管されているタンスの奥深くに隠されている。絹の袋に入っており、高級な素材と精巧な設計がなされたものだ。これは綾人が成人した日に、母から贈られたものである。
神の目
何年も前のある夜のこと。病気で寝たきりだった父が突然、綾人をそばに呼んだ。
その夜、病で疲弊していた今までと比べ、父の様子は少し違っていた。ただ、厳かな表情をしてはいるものの、彼の目に浮かんでいる心配の色は隠せていない。
どうにか気力を振り絞り、父は綾人に聞く——「今日の修行は終わらせたか?」「夕食はしっかりと食べたか?」「剣術の修行に進歩はあったか?」
綾人がそれに一つ一つ答えると、父は満足気に微笑みながら頷いた。しかし、すぐにまた顔に陰りが差す。何かを言いたいのに、言えずにいるようなそんな表情だった。
長い躊躇いの後、母の憂いに満ちた眼差しを受けて、父は重々しく口を開いた——
「綾人、これを…覚えておきなさい。この先、神里家がどのようになろうと、綾人は私たちの長男であり、綾華の兄であり、そして神里家の紛うことなき後継者だと。」
安心して休んでいただくよう父に伝えた後、綾人はゆっくり寝室へと向かった。
扉を開けてすぐ、光り輝く「神の目」が文机の上にあることに気付いた。
綾人は幼少の頃、「神の目」とは神の眼差しを象徴しており、人々の願いに応じて生まれるものだと聞いた。
何か大義があるわけではない。ただ、一族が末永く繁栄し、家族の安寧を守ることこそが、幼い頃より綾人の志すものである。
「神の目」がこの時分に現れたということは…彼が責任を担うべき日が来たということなのかもしれない。
そこまで考えを巡らせると、綾人は使用人に明かりを点けさせることなく、文机の前に正座した。
様々な事柄が、まるで渦潮のように彼の脳裏をよぎる——
父は重い病を患い、母も体調が芳しくない。一族には当主もおらず、政敵たちは神里家の地位と権力を狙っている。
妹はまだ幼く、心安らかな成長のためには己が身を賭して事に当たらねばならないだろう。幕府官界はまるで暗礁に囲まれた海域、何をするにも慎重でなくてはならない…
代々神里家に仕える「終末番」も当然見捨てることはできないだろう。神里家が衰退する中、周りにいる使用人にまだ信頼できる者がどれだけいるのか…
それから異郷出身のトーマについても。彼は友人であり頼りになる存在だが、低迷する神里家に対して本当に何も企てはしないだろうか…
乱雑に存在する事柄すべてが、綾人の脳内で整理されていく。その情報の渦の中心にあるのが、彼の変わらぬ信念だった——
未来のため、家族の安寧のため、使えるものは手段を問わずすべて使い、邪魔するものは一切の代価を惜しまず排除する。
その夜、室内には明かりが点くことなく、神の目だけが彼に付き添う唯一の照明となった。
黎明が訪れ、その日、最初の光が窓から文机に降り注いだ時、すべてを迎え入れる準備を終えた一族の若き長男がそこにはいた。