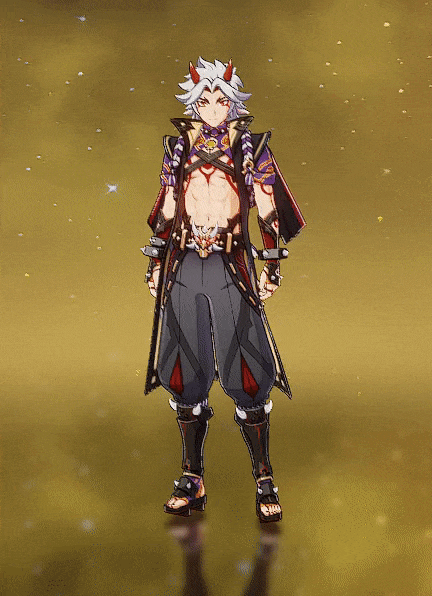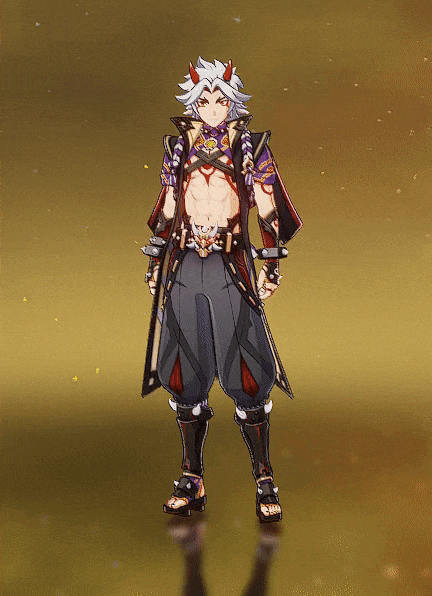キャラクター詳細
花見坂を歩いていると、「荒瀧一斗」という鬼族の青年が必ず目に留まるはずだ。
目立つ鬼の角とよく通る大音声。だが、それら特徴を抜きにしても、子供たちと夢中で遊ぶ荒瀧一斗の姿は人の目を引くことだろう。
花見坂には大勢の職人が集い、忙しない日々が流れている。しかし、彼という存在は暇を持て余しているようだ。
自称「荒瀧派の初代親分」一斗は、かつて町内での些細な喧嘩が原因で天領奉行に職務質問をされたことがある。しかし、二分と経たずに彼の言葉は打ち切られ、「無職」と記録された。
ただ「無職」というのは些か妥当ではない。幕府の認可を得ていない荒瀧派だが、その雑務以外にも生計を立てるため彼は臨時の仕事をしているのだ。その頻度は一日働いたら三日休む、という非常にゆったりとしたもの。
ゆえに「四分の三は無職」と記録したほうが妥当だろう。
キャラクターストーリー1
客観的に見て、稲妻城での一斗の評判は決して良くはない。
悪人とまではいかないものの、善良な町民でないことは確かだ。
ただ、彼の恐ろしさを言葉で表すのなら、稲妻の家庭で子供を言い聞かせる際、「父ちゃんと母ちゃんの言うことを聞かないと、荒瀧一斗にお菓子を奪われちゃうよ!」と脅される程度のもの。
無論、荒瀧一斗に菓子を奪われる可能性は十分にあり得ることだ。そのため、「袋貉に山へ連れて行かれる」や「将軍様に神像にはめ込まれる」よりも効果はてきめんである。
しかし、「奪われる」という言葉には少々語弊があるだろう。一斗は真っ向から勝負を挑むことで、子供から菓子を手に入れているのだ。
子供に勝って菓子を奪うなど、卑劣な行為だと思う人もいるかもしれない。だが、相手が五歳児であろうと、尊き雷電将軍であろうと、一斗は勝負に対して真剣であるべきだと考えている。
たとえ子供相手でも一斗が素直に負けを認められるのは、この純粋な信条を持っているからなのだろう。
大人たちは一斗に不満を抱いている。しかし、一方で子供たちは、この鬼族のお兄ちゃんを良い遊び相手だと思っているようだ。
荒瀧一斗は巷の様々な遊びに精通しており、どのような遊びであろうと楽しみながら挑む。それだけではない、もしいじめられている子がいれば、必ずその子の味方をするのが荒瀧一斗なのだ。
ここ最近、子供たちが夢中なのは一斗との「虫相撲」である。
この昔ながらの遊びは単純ながらも、非常に苛烈なぶつかり合いによって、見ていて飽きることがない。そして何より重要なのが、他の遊びに比べて一斗の勝率が悪くないという点だ。
好感度Lv.2後に解放
キャラクターストーリー2
長いこと、天領奉行は「荒瀧派」をたまに騒ぎを起こすだけの、さほど注意の払う必要がない集団だと認識していた。
この一派の構成員は十人にも満たず、結成日でさえ人によって意見が分かれている。
晃の場合、数人のゴロツキに絡まれていたところを一斗に助けられたことがあり、その日を結成日だと考えているようだ。ゴロツキ相手に一斗は七回も膝を突かされたのだが、まったく負けを認めず、ついには呆れ果てた相手が去って行ったという。そして、一斗は倒れていた晃に手を差し伸べ、こう言った——「お前も今日から荒瀧派の一員だ!」
元太と守の場合、ある年の暮れ、稲妻の郊外で一緒にうずくまりながらスミレウリを焼いた日を荒瀧派の始まりだと思っている。
その日、彼らは無一文で腹を空かせていた。すると、焼いたスミレウリを食べながら、一斗は感慨深げにこう言ったのだ——「荒瀧派の野郎ども、これからは毎年こうやってスミレウリを焼いて、一緒に食おうぜ!」と。
ただ残念なのは、元太も守も、そのような出来事は懐かしむべきものではないと考えている点であろう。
久岐忍の場合、初めて一斗を牢屋から救い出したときこそ、荒瀧派が結成された日だと考えている。なぜなら、そのとき初めて公文書に「荒瀧派」という名が記録されたからだ。
そして一斗の場合、「荒瀧派」の三文字が頭に浮かんだ瞬間から存在していると思っている。
残念ながら、この考えがいつ生じたのか、もうほとんど覚えていない。
しかし、幼い頃から一斗の面倒を見てきた鬼婆婆は、荒瀧派が結成されたことなどないと考えている。
彼女にとって、それはただ一斗と仲間たちが集まっているだけに過ぎないのだ。
好感度Lv.3後に解放
キャラクターストーリー3
稲妻には、古くから妖怪の一族が住んでいる。
「白辰狐王一脈」や「天狗党」に加え、「鬼人衆」もこの地で活躍をしてきた。
これら妖怪の大半は、人間が羨むような特殊能力を備えている。だが鬼族の場合、特別な力をほとんど持っていない。
頭に生えている鬼の角を除き、特徴と言えるのはその気性の荒さと厄介事をよく招いてしまう点のみ。
また鬼族が豆を恐れるという言い伝えがあるが、これはすでに学術的に証明がされている。
実は、鬼族の大多数は豆にアレルギーを持っているのだ。ただ鬼族の血は時の流れとともに次第に薄まり、そのほどんどは軽いアレルギー反応を起こすだけとなっている。
しかし、悲しいことに非常に深刻な豆アレルギーを持っている者がいる、それが荒瀧一斗だ。豆を食べるのはもちろんのこと、肌に触れれば全身にかゆみが走り、呼吸もままならなくなってしまう。
そのため、普段は大雑把で周りを気にしない一斗も、「豆」にだけはいつも警戒しているようだ。
荒瀧派の一員は親分への忠誠心から、一斗と飲みに行っても決して枝豆を注文しないという。
なお、豆を使った食べ物の中でも、一斗がもっとも恐れているのは「油揚げ」である。本人曰く、見ただけで三日は吐き気が続くそうだ。
好感度Lv.4後に解放
キャラクターストーリー4
「油揚げ」で真っ先に思い浮かぶのが、ある勇ましくも悲壮に満ちた勝負のことだ。
その勝負の始まりは、日常の小さな揉め事であった。一斗が給料を貰った日、行きつけの屋台へ行くと、一つしかない店の席に狐耳の女性が座っていた。
その席を奪おうとする一斗であったが、次第に狐耳の女性と口論となる。そして、その席を賭けて真剣勝負(必要のない)をすることとなった。
話し合いの結果、勝負の形式は一斗が決め、その具体的な内容を狐耳の女性が決めることになった。
働いた後で腹を空かせていた一斗は大食い勝負を選び、狐耳の女性は食べる料理を選んだ——それが「きつねラーメン」である。
ラーメンの中に油揚げが入っていることを想定していなかったのは、一斗にとって致命的なものであった。しかし、持ち前の根性で勝負を乗り切り、なんとか鬼としての威厳を保つ。
そんな一斗の迫力に腰を抜かした店主は、その争いの火種となった席を彼に渡したそうだ。
それら数々の勝負をくぐり抜けてきた一斗であるが、その中でも心残りが二つある。
一つは天領奉行によって神の目を奪われた際、自分を打ち負かした相手である九条裟羅との再戦が果たされていないことだ。
今なお、九条裟羅は町中での相撲を拒否しており、一斗は不満を抱いている。
そして、もう一つが幼い頃にあったある出来事だ。ある日、天狗の子供と口喧嘩となり、白狐の野で相撲を取ることになった一斗。しかし、その最中に二人とも山から転げ落ちてしまうということがあった。
結局、足を挫いて歩けなくなった一斗を、天狗は家まで運んであげたそうだ。もちろん、勝敗は決まらないまま終わっている。
両方とも天狗が絡んでくるとは、なんともツイてねぇ!
天狗っつうのは痩せてやがんのに、どうしてあんな力が強いんだ。
好感度Lv.5後に解放
キャラクターストーリー5
赤鬼と青鬼の話は、どの鬼も子供の頃に聞いたことがあるだろう。
優しくてお人好しの赤鬼が、悪事を働く青鬼を倒し、人々から鬼族の尊重を勝ち取る物語。
これは一斗が幼い頃に一番好きだったお話だ。赤い鬼の角を持つ一斗は、赤鬼の血筋を誇りに思っている。
しかし、そんな子供の純粋な思いは、ある事件をきっかけに揺れ動いた。
一斗の住む村で、凶悪な強盗や暴行事件が相次いだのだ。人々の疑惑の目は、鬼族である荒瀧の家に向けられた。
一斗は、当時のことをもうほとんど覚えていない。しかし両親に連れられて村を出るとき、村人たちから向けられた嫌悪感と警戒心に満ちた視線、そしていずれ幾度も耳にすることになる言葉を、彼はいまだに覚えている。
「やはり鬼はどう足掻こうと鬼のままなんだ。」
いつの時代においても、人間から見れば鬼は鬼でしかないのだ。何も悪いことをしていないのに故郷を追われた両親と比べたら、人々に恐れられている青鬼のほうが幾分かマシなのかもしれない。
両親が病死した後、幼い一斗は町中を彷徨い、鬼の悪口を言う者がいれば喧嘩を吹っかけていた。
しかし、殴られるのはいつも一斗のほうである。彼は地面に何度倒れようとも諦めず、厄介な相手だったことだろう。
だが、このときの一斗はまだ子供。ゴロツキどもに痛い目に遭わされ、飢えと疲れで体は悲鳴を上げ、やがて路上に倒れてしまう。
そんな満身創痍な状態の中、一斗はある人間の老婆に助けられた。
「おい、俺様は鬼だぞ!どうして助けた?」「お腹が空いとるんじゃろう?今ちょうどおかゆが出来たところじゃ。」
「聞いてんのか、俺は鬼族だ!俺の頭に生えてる角が見えないのか?」「もちろん見えとるとも…それより、おかゆはどうだい?」
「あああッ!もう、話を聞けってんだ——ゴホッ…ちっ、婆さん…じゃあ、おかゆを一杯頼む…」「ああ、少し待っとれ。」
好感度Lv.6後に解放
「豪歌会」
年の瀬を目前にして、荒瀧派はどう年を越そうかと話し合っていた。
一般的な組織と異なり、荒瀧派は決まった活動拠点を持たず、モラの蓄えもない。きちんとした場を設けるのは些か難しいことだろう。
案の一つである「スミレウリの会」は却下された。スミレウリ自体を焼いて食べるのは問題ないが、食料がスミレウリだけなのはあまりにも惨めだからである。
「虫相撲の会」も悪くない案であったが、年の瀬はオニカブトムシの繁殖期ではないため、いまいち闘志に欠けている。
結局、くじ引きにより「豪歌会」なるものが選ばれた。
これは一斗が提案したもので、崖の上に立ち、潮風に吹かれながら熱き想いと未来への希望を歌にするというものだ。
それを知った面々は心の内で拒絶したという。海に向かって熱唱するくらいなら、スミレウリを食べているほうがマシだと。久岐忍はその場で休暇を取って実家に帰りたいと言い出した。
しかし、豪歌会は予定通り開催されることとなる。大声で熱唱するのは実に気持ちのいいこと。そして、意外にも一斗の歌唱力は見事なものであったという。
好感度Lv.4後に解放
神の目
ある朝、眠りから覚めた一斗が腰の下に手をやると、そこには神の目があった。これは一斗が花見坂に来てもう何年も経ち、生活がある程度安定していた頃の出来事である。
「父ちゃん、母ちゃん、爺ちゃん、婆ちゃん。それに鬼婆婆…とんでもねぇことが起きちまった!」
神の目を見た瞬間、一斗の頭にはそのような言葉が浮かんだという。
その日、彼は人に会うたび神の目を見せびらかしては鼻息を荒くし、神の目を下敷きにしてできた腰のくぼみを見せつけた。皆、耳にたこができるほど聞いたことだろう。
しかし数日後、荒瀧一斗の話す内容は一変していた。
「神の目を見た瞬間、俺様の心は一寸たりとも動かなかった。なぜなら俺様は荒瀧派の初代親分だからな、神の目を手にするのも当然と言える。
そもそも、人の価値なんざぁ、神の目で量れるもんじゃねぇ。そうだろ?」
だが目敏い人であれば、一斗が非常に柔らかな眼鏡拭きを買ったことに気づいていることだろう。
つい先日、『月刊閑事』の質問欄にある投稿が寄せられていた。
「ヒナさん、神の目をより輝かせるためには、どうしたらいいんだ?他のやつらよりもピカピカにしたいんだが…」
それを読んだ荒瀧派の面々は、興奮しながら一斗にその本を見せた。しかし、長年ヒナさんに絶大な信頼を寄せてきた一斗が、一瞥しただけで本を手放したのは想定外だっただろう。
好感度Lv.6後に解放